コースの中でトマトを使えないかと考える。洋食色の強いトマトを和食の中で使うには、定番となっている和食技術、例えば天ぷらのタネにするとかすき焼きの具にするとか、そういうふうに使うか、あるいはトマトの外観をなくして、味だけを抽出して使うかのどちらかだろうと思う。今回はトマトを潰して濾して、透明な汁だけを出汁代わりに使うやり方を試す。みりんと薄口醤油で味を調えると、鰹出汁の八方地にすだちを絞ったような清涼感のある味になる。枝豆も合いそうだしとうもろこしも合いそう。ハモも合いそう。
日刊鶴のひとこえ
5860声 横目
2024年07月23日
顔は動かさずに目だけ動かして横目で人を見る仕草に出会うたびに、本人は自分がこちらを見ていることに誰にも気づかれていないと思っているような気が勝手にしてしまう。こっそり覗いている、という雰囲気が漂うのである。もちろんその横目は敵意のない横目の場合だが、こっそり覗いている気になっていると思うと妙にかわいらしく、いとおしくなってしまう。
5889声 癖はなかなか治らない
2024年07月22日
自分の意見を言うことに囚われすぎると、とりあえず否定するという最悪の癖が身についてしまうということがある。それはもっと巻き戻すと、とりあえず否定してしまう人は自分の意見を言い過ぎる他者と一緒にいる必要下にある人なのかもしれない。やるせないと思うのは、もう周りには自分の意見を言い過ぎる他者はいないのに、とりあえず否定する癖だけが身に付いてしまい治らない場合である。それにしても今日のトビハタはおいしかった。
5888声 白麹ビール
2024年07月21日
電車とバスを乗り継いで川場村へ。オクトワンの竹内さんの新作白麹ビールが目当て。電車もバスも本数が少なく、ビールが飲める時間の2時間以上前に到着した。高崎は朝から暑かったが川場村も暑い。道の駅で少し腹ごしらえをして近くにできた温泉施設で風呂に浸かる。バスもタクシーもないため、そこから白麹ビールの会場まで歩いた。なだらかな上り道を30分、湯上がりの身体から汗が吹き出す。「ビールはまだか」セミの鳴き声がそう言っている。その後飲んだ白麹ビールのおいしかったこと。
5887声 常に悩んでいる
2024年07月20日
7名満席のお客様。それぞれにご自分のペースで楽しんでいただいている様子。品数が多いため完璧に準備したつもりでも終わるまでに2時間以上かかってしまう。とにかくその間中こちらは必死。手抜かりなく準備すること。始まったら一時も気を抜かぬこと。ただ、準備も営業も生き物だから揺れ動く。そこに合わせながら進むから常に悩んでいる。
5886声 シンコの季節
2024年07月19日
シンコが始まる。まだ親指よりも小さいサイズ。20尾程度なのにいつもの仕込みにプラス1時間半かかった。昨夜は暑くてあまりよく眠れず身体が重いので日帰り温泉へ。常連の年寄りが昨夜寝ている間に目が覚めた数を報告し合っていた。「俺は2回」「俺は3回目が覚めた」「俺は起きなかった」みんなよく覚えていることに感心した。
5885声 日々試作
2024年07月18日
一品目に出しているとうもろこしの寄せ物を茶碗蒸しヴァージョンに。今まではゼラチンで寄せていたが卵で寄せたらどう変わるか試してみた。やはりゼラチンのつるんとした食感のほうがしっくりくる。鰹がいいので薬味もいくつか揃えてみる。長葱の青いところ、白いところ、あと万能葱と準備して食べ比べるが、結局玉葱が一番合う。薬味で印象が変わるから薬味は大事である。営業前にお腹がグルグル言い始めた。きっと葱の食べ過ぎだ。とにかく腹が弱い。
5884声 今日は
2024年07月17日
昨日も19時過ぎには横になる。そのまままた朝の5時頃まで寝たまま。毎日毎日寝たままオジサンである。昨日の足踏みで長らく張っていたお腹が少し楽になったようだ。恐る恐る腕立てと腹筋をしてみる。昨日までよりも回数ができた。そのまま着替えてジョギングへ。体調がいまいちでも走り出すと走れたりすることがあるからなるべくジョギングの格好に着替えて外に出るようにしている。今日はなんだか調子がいい。調子がいいだけで、あるのかどうかもわからない不安は雲散霧消する。だからもちろん逆もあって、調子が悪いだけで、あるのかどうかもわからない不安に襲われる。30歳の頃にあたりまえに安定していた体調は40歳で安定率2/3くらいになって、今は半分以下くらい、という実感。一方で30歳の頃の雑な不安定さは、経験が増えたことによる理解か、あるいは慣れか諦めか、いずれにせよ他者の気持ちも自分の気持ちも少しは理解できるようになり、安定率を増している。さて、若さゆえ体力はあるが雑で(それは時に残酷で)不安定なのと、老いがゆえ懐は多少深くはなったが調子がよくないため不安定なのと、どっちが幸せなのか。今日は少し体調がいいらしく、だからこういうふうにも言葉が出てくる。不安定な体調は雑な態度を招く。難しいよね。そういえば、昨夜もいろんな夢を見た。覚えているのは、軽のワンボックス自動車にヘリコプターの羽がついていて、中は満席。乗っているのはスケートの練習に行く選手たちで、その中に私もいた。その空飛ぶ軽自動車の運転手が何故か小池百合子東京都知事で、空をビュンビュン飛ばしながら目的地まで送り届けてくれて、途中でみんなに焼肉をごちそうしてくれた。もし今日が投票日だったら小池百合子に一票入れていたかもしれないな。寝過ぎは夢も現実もわからなくするのかもしれないな。
5883声 中森明菜
2024年07月16日
昨夜19時過ぎに寝て5時半までそのまま。たくさん夢を見た気がするが、中森明菜が出てきた夢だけを覚えている。タクシーに乗っていたら中森明菜が同じタクシーに乗ってきた。市場へ行ってから仕込み。海はまだ時化が続いているようで魚は高い。夜に予約がないからか仕込みに追われることもなく、それぞれの仕込みを落ち着いてできた。鮑がとてもいい。午後も続きの仕込みをしてから足踏み整体へ。施術の強度が上がった気がする。毎回考えながらやってくれているのが伝わる。
5882声 同線に問題あり
2024年07月15日
シンキチ店番の日。シンキチのカウンターはお客様との距離が近い。自分で設計したくせに近いなと感じる。同線はもう少しスムーズにいく配置を考えたほうがいい。場所が変わるだけで慣れない動きが多くなって疲れも多くなる。鮨を食べに来てくれたお客様が多く、多めに炊いたシャリも終わった。忙しく営業が終わり準備したものが概ね終わったとき、そこでようやく深く吐いた息に乗って生きている感覚がじわじわと湧いて出てくる。幸せが醸成される瞬間である。
5881声 寿司トレ
2024年07月14日
葛根湯が効いたのか寒気は治まる。腹が張っている感じは変わらない。身体は動くのでシャリを炊いて握りのトレーニングをした。右手の親指の使い方にいい気づきがあった。トレーニング大事。
5880声 体調いまいち
2024年07月13日
朝起きるが体調はあまりよくなく、昼過ぎからは寒気もしてきた。いつも以上に眠れるのは体調がよくないときのしるしである。今年は体調が万全というときが少ない。1月半ばにコロナに感染し1ヶ月近くだめで、4月には花粉と黄砂で咳が止まらなくなった。その後腰痛となりコルセット生活、少しよくなってジョギング中に転倒、と、まぁ、普段から何かの痛みやだるさに耐えている時間の多いこと。今日はひとこえを書くのがやっと。また寝ますよ。おやすみなさい。
5878声 ビールの仕込み
2024年07月11日
朝からビールの仕込み。マッシュの温度を変えてみた。普段はやらないα-アミラーゼ分解の温度帯を長めにとってみる。ビールの味にボディが増すはずだがどうなるか。濃い一番麦汁を取り置き別釜で長時間煮沸する方法も試す。プリンのカラメルソースを作っていて思いついた。味に香ばしさを加えたい。
5877声 整体の日
2024年07月10日
午前中はタンクの洗浄、ビールの仕込みの準備などして午後は整体。首が痛いと思っていたが、かなり固まっていたと言われる。夜中に足が熱を持ってむくんでいる感覚でよく眠れず。
5876声 シャリ
2024年07月09日
シャリがよくなった。些細なことに気づきやってみたら炊き上がりがよくなった。店でワインを出すためワイングラスを気にするようになって、0.何mmの口あたりや形状の違いによるワインの味の違いに神経がいくようになった。おそらくその経験が大きくて、シャリを口に入れたときの感覚にも影響を及ぼしている。シャリが理想に近くなってきた。一つ決まるとそこから他のことも影響を受ける。どんなネタが合うのかだけでなく別の料理やビールの味の解像度もそこを基準に上げていきたい。シンキチでアルバイトをしていた子が旦那さんと方に来てくれた。あまり気持ちを表に表さないタイプだと思っていたがおいしそうに寿司を食べていてよかった。
5875声 青い旨味
2024年07月08日
昨日夜の8時半頃に予約が入り朝から市場へ。仕事が少ないと酒量が増えてしまう。不規則な暮らしでよく破綻せずここまで来た。いいや、自分の性質と確かな老化を掛け合わせれば今からでもいつ破綻してもおかしくない。海のない高崎は猛暑だが一方で海は時化らしい。それでも朝一番に行く特権でその日のいい魚を仕入れることができる。今日は鰹と胡麻鯖が当たり。お客様がこれを食べたときに目を見開くのが目に浮かぶ。久しぶりにコチも仕入れた。しっかり神経抜きの処理がしてある。鯵のような、青い旨味がある。瓜のよう。脂が少ないため刺し身で食べるしかないように感じるが、この旨味をふわふわ食感にできないかと考えしんじょうにすることにした。卵白と合わせて少し油を足してミキサーにかけ、型に流して低温で蒸す。間には薄切りにした生麩を挟んだ。提供前に温め直して赤出汁の椀種とする。刻んだみょうがを添えて。いい感じにできた。
5874声 七夕猛暑
2024年07月07日
暑い。まだ七夕である。ヤフーニュースで今日の予想最高気温が41℃と出ていたが間違いではないか?そんな気温を経験した記憶がない。寝苦しい夜で睡眠が足りず、二度寝をして午前中は寝て過ごす。午後は冷蔵庫の整理をしながら少し料理をして3時頃から飲み始めた。
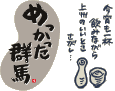
 Copyright 2007-2024 Crane Dance. All Rights Reserved.
Copyright 2007-2024 Crane Dance. All Rights Reserved.