今日は朝からオンライン含めて打ち合わせが6本。交付金の申請期限でもあり、係員が作った計画書を最終チェック。設計デザインも方向性の検討が大詰め。年度末に向け、全てをクロージングさせて行かなければならない。とはいえ残業はせず娘を迎えに帰る。保育園から帰ってくる際に、明日は飲み会なのでお迎えはお母さんだよと伝えると、小躍りして喜んでいた。。
日刊鶴のひとこえ
5709声 世界と
2024年01月24日
今日はJICAやデジタル庁と本プロジェクトに係るODAの活用についてオンライン会議。こちらの計画にかなり興味を示してくれ、非常に協力的でありがたい。国家的プロジェクトに育てるためにも、協力者は一人でも多く獲得したい。ODAと絡んで仕事ができることがあろうと思っていなかったので、個人的には嬉しい限りである。
5708声 北千住
2024年01月23日
今日はデジタル庁でITの業界団体やグルーバル企業に対し、本プロジェクトを説明し将来的な協力を要請しつつ意見交換。グローバル企業の幹部が本県出身ということもあり、本プロジェクトの支援についてカリフォルニアの本社に問い合わせて貰えることとなった。業務終了後、北千住まで足を伸ばして肉豆腐で有名な名店「大はし」へ。約2年ぶり。いつもどおり大将が威勢の良い声で注文を取り、リズミカルに酒肴を運んでいる。無駄なおしゃべりや動きは一切ない。ここは海鮮も安くて旨い。関鯖と白エビの刺身で日本酒をちびちびやり、名物の焼酎梅割に串カツを合わせた。ふと、子供を連れてくるには後何年かかるか考えて苦笑し帰路についた。
5707声 夢の余韻
2024年01月22日
宿泊した和洋中華、アジアンなど各国の料理が彩りよく並ぶビュッフェで朝食を取った後、部屋に戻り、青い空と海を見ながらビアを空ける。娘はルームにあるコップやポットでおままごとをしている。リゾートホテルでボーッと景色を見ながら酒を飲む時間がたまらなく好きである。このホテルはチェエックアウトが12時と遅いのでゆったりできる。もう1本飲んで帰路についた。
5706声 夢の国
2024年01月21日
当初は午前中で雨が止む予報であったが、昼を過ぎても雨はやまず生憎の天気。ただ、お陰でお客さんも少なく、アトラクションはスムーズに乗ることができた。ミニーちゃんに会った娘は、緊張のあまり鯱張っていた。乗り物系は怖がって泣いたりもしていたが、It’s a small worldはお気に入り。帰りがけにようやく晴れて、シンデレラ城に沈む夕日が赤々としていた。帰りのベビーカーの中で、「せかいはまるい~せかいはまるい~」と歌いながら両手で投げキッスをしていた。普段は近所のおばさんに挨拶されても横を向いたり、親の後ろに隠れたりする娘が、世界を祝福したい気分になったのであれば、連れてきた甲斐もあった。さすが夢の国。
5705声 明日は
2024年01月20日
明日は母子の誕生月に恒例とされつつあるTDLへ。娘は何ヶ月も前から楽しみにしていた。昨日も保育園に迎えにいくと、「○○ちゃん、どなるどのくつしたはいてるからディズニーランドいけるかな?」と確認していた。ミニーちゃんの動画は毎日見ている。妻は学生時代にTDLでバイトをしていた程、筋金入のファンである。ここまでプレッシャーを受けていれば連れて行かない訳にはいかない。
5704声 想定外
2024年01月19日
今日は国の交付金の関係で想定外の大騒動がおき、終日その対応に追われる。来週が申請期限だが、難題が降りかかる。なるようにしかならないが、できる限りのことはする。
5703声 葬儀
2024年01月18日
今日は高校時代の部活の友人の親の葬儀。仕事を中抜けして焼香だけしてきた。他の同期2人と昼食を食べながら子育て談義。家より子供が大きいので色々と参考になる。卒業して30年近くになるが、何かあれば集まってくる。
5702声 保育参観
2024年01月17日
本日は保育参観。9時前から15時半までの長丁場である。先ずは狭い園庭を0歳児~3歳児までが音楽に合わせて走ったり歩いたり。ラジオ体操を経て、それぞれの教室に向かう。娘は3歳児なので、一番上のクラスになり、二階の拾い部屋があてがわれている。自分の持ち者を所定の位置に置く。水筒、ハンカチ、鞄は自分のロッカーへ。みな毎日のことなのでちゃんとできる。その後外部講師の英語の先生が来てEnglishの時間。娘はEnglishが好きなので、色当てや英語での体操を楽しそうにしていた。その後、絵本を読んだり給水タイム、仏教系なので読経も日課のようだ。般若心経をそれっぽく諳んじていてびっくりした。給食も専門職員の作りたてなので、家で食べるより集中して食べていた。ご飯を食べたら順番でトイレに行き、ボタンのパジャマに着替える。まだ上手に着られない子もいる。そのまま1階に移動して2時間ほど昼寝。その間に参観した親にも給食が振る舞われる。久しぶりに米をたべたが美味しいご飯。お変わりしている親も多かった。昼寝の後、みんなでおやつを食べて絵本を読んだり。椅子取りゲームもしたが、娘は最初から試合放棄。後で聞いたら怖いとのこと。それも分かる。15時半になり家族3人で帰宅した。親が近くに居たので終始甘えモードでいつもの様子とは少し違ったと思うが、保育園での1日の過ごし方が分かって安心した。どの先生もしっかりしていて優しい。親や親族以外で真剣にこどもの成長を考えてくれている存在があるのがありがたい。同級生や下級生と多くのこどもに囲まれ社会性も身につけさせていただいている。家で親と居るよりよほど学びと成長があると思う。
5701声 変わりゆくもの
2024年01月16日
娘がおむつ姿で遊んでいる。最近はうんちはトイレでするし、おしっこも大体トイレでできるようになった。おむつが取れるのも時間の問題だ。そう考えると。短い足にポテッとふくらんだおむつ姿がたまらなく愛しく見えた。そんな話を妻にしたら、こっそりとお尻をフリフリして踊っている娘の動画を撮って送ってくれた。
5700声 娘とのお風呂
2024年01月15日
今月の初め頃に自分で髪を洗えるようになったと書いたが、3日ほどで飽きたらしく、親に洗って貰うことに退行。最初、好奇心でやるが面倒くさくなって続かないというのはありがち。最近のはやりは、お風呂のひらがなマットで自分や友だちの名前を指さすのと、入浴剤をお風呂でなくバケツにいれ、シャベルで少しづつお風呂に入れること。さっさと入れて欲しいのが本音だが好きにさせている。冬の寒さもあってか入浴時間は長く、ゆうに30分は一緒に入浴している。そういえば、赤ちゃんの頃から温泉も嫌がらなかったし、熱いお湯も割と大丈夫だった。
5699声 妻のお陰で親孝行
2024年01月14日
娘の七五三の着物姿を両親が見てないというので、妻がわざわざ娘の着物を持ってきた。この辺りの心遣いは人間の機微に触れる。娘も着飾って嬉しそうだ。せっかく着物を着たのでおじいちゃんと近所を散歩。鼻歌を歌ったり、突然走り出したり、かなりテンション高い。親父も嬉しそうだ。ほんとに3才児は居るだけで周囲をキラキラさせる。
5698声 ぬるめのラーメン
2024年01月13日
今日は渋川の実家に帰りビアを飲みつつラグビーの大学選手権の決勝を観戦。大学の同期は現地で観戦している。途中落雷の危険による中断や降雪の中のタフな環境での試合になった。荒天による何かを期待したが結果は母校の完敗。夕方から高校の部活の同期との新年会。卒業して30年近くになるが毎年やっている。子連れで来るやつや離婚したやつ、能登半島地震の救援から戻ってきたやつなど、近況を報告し合う。〆は中学生の時から通っている中村ラーメンと決まっている。高齢の夫妻がまだお元気で良かった。このぬるめの味噌ラーメンをたべると新しい年が始まったなと思う。来年もまたここで。
5697声 いっこづつ
2024年01月12日
今日は娘と同年の娘さんがいる家族と新年会。家族ぐるみで付き合っている数少ないお相手。娘が会いたがっていた。保育園の帰りに今日は○○ちゃんとご飯だよと言うと。娘がひとしきり喜んだ後「はるなちゃんできればいっこづつ(一人づつ)あいたい。いっこづつならかわいいかわいいっていってあげられるけど、たくさんいるとわーってなっちゃう」と言った。なるべく個を尊重したい気持ちをちゃんと説明できて、父ちゃん嬉しくなったよ。
5696声 働き方の多様性
2024年01月11日
本日は在宅勤務。環境が整い、職場に居るのと同じように仕事ができる。午前中からオンラインのミーティングを何本かこなし、黙々と作業に集中できる。終業時間が終われば、すぐ子供を迎えに行くことができる。働き方の多様性は子育て世代にはありがたい。
5695声 晩餐
2024年01月10日
今日は尊敬する職場の上司を囲む会。クリエイターなどおなじみの面子が年2回程集まっている。方も検討したが既に予約で一杯だったので、通町のやたいやに。毎回、気づきのある話が聞ける。コース料理を楽しみながらゆったりとした時間を過ごした。
5694声 一番星
2024年01月09日
本日は予算のトップヒアリング。冒頭のマスコミ撮影を経て、全事業の中で一番にヒアリングが行われた。改めてこのプロジェクトに係るトップの強い思いを再認識した。夕方、保育園からの帰り道、一番星を見つけ娘とみていたら、「おとうさん、まえ、おんせんから出たとき、なんのお星さまみてたの?」と。何かの瞬間を思い出したようだ。いつのことか、どこでの話か思い出せないが、何のお星さまだったかね。また見ようね。と返した。
5693声 デイキャン
2024年01月08日
娘がみずうみでキャンプしたいというので、家族で榛名湖へ。うっすら雪が積もっており、風が強く湖面も凍る気配がないほど波だっていた。湖畔に降り立ったがあまりの寒さにデイキャンプどころではないと妻と話し、少し湖畔で娘を遊ばせて帰ることに。遊べるほど積もってなかったが、小さな雪の塊を車内に持ち込んでいた。こうゆうところがこどもっぽくて良い。帰りの車内で娘が「キャンプはどうした?」と。寒かったから諦めたんだよと言うと。「さむいからあきらめたじゃないんだよ!きゃんぷはどうした」とわめきだした。誰かに諦めるんじゃないよなんて直言されたこともなかったので、思わず笑ってしまった。山から下山したデイキャンプ場で急遽焚き火をおこして昼食を食べた。山の中では娘ほんと元気だ。木を拾ったり梢を眺めたり森をどんどん進んでいく。やはり時々は自然の中に連れ出したい。
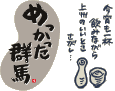
 Copyright 2007-2024 Crane Dance. All Rights Reserved.
Copyright 2007-2024 Crane Dance. All Rights Reserved.